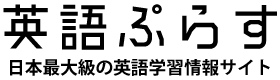自動詞と他動詞の違いと見分け方|覚え方もわかりやすく例文と一覧で解説
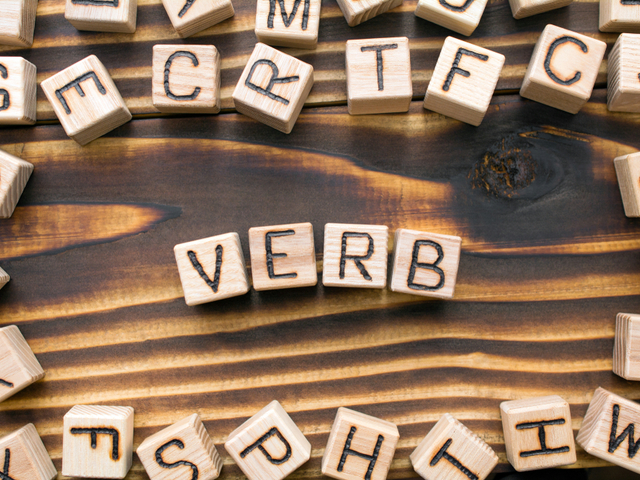
英語を学ぶ上で避けては通れない自動詞と他動詞。どのように見分けていますか?
覚えるべきだとは分かっていても、見分け方が分からず「覚えるしかない」と諦めている方も多いはず。知恵袋などで調べた経験もあるのではないでしょうか。
そんな自動詞と他動詞は、中学科目や高校科目の英語学習で習います。しかしいざ英作文に挑戦すると、目的語はどこに入れる?前置詞は必要だっけ?と迷ってしまいがちです。
今回は自動詞と他動詞をテーマに、両者の見分け方や覚えておきたい一覧表など英作文や和訳に役立つ情報をご紹介します。基本をおさえて動詞の達人になりましょう!
英語の自動詞と他動詞の違い

動詞は、be動詞と一般動詞、自動詞と他動詞などと分けられます。
しかし、すべての動詞が自動詞か他動詞に分類されるわけではありません。そのため、動詞の使い方として自動詞や他動詞があると考えた方がわかりやすいです。まずはその点をしっかり頭に入れておきましょう。
それでは、自動詞と他動詞は、どのような使い方をするのでしょうか?例文を交えながら、わかりやすく説明します。
自動詞と他動詞の違いと意味①自動詞とは
自動詞とは目的語を必要としない動詞のことです。おそらく学校でもそう習った方が多いでしょう。これがまず基本です。主語+述語で完結する文章で、述語の役割を務めるのが自動詞。下の例文を見てみましょう。
彼は歩いた。
He walked.
主語(He)+述語(walkの過去形)で完結しています。このような文は、主語の動作に関するものが多いです。walk(歩く)も動作を表す単語で、主語であるHeが動作の対象となります。
自動詞と他動詞の違いと意味②他動詞とは
他動詞は、目的語を必要とする動詞です。自動詞の例文としてHe walked.をご紹介しましたが、実はwalkは他動詞としても使えます。下の例文を見てみましょう。
彼は犬を散歩させた。
He walked the dog.
同じwalkですが、自動詞と他動詞とでは意味が違います。他動詞の場合、「~を散歩させる」という意味になり、助詞である「を」が動詞に含まれます。
日本語でいえば、犬(目的語)+を(助詞)+散歩させる(動詞)という構成ですが、このうち助詞(を)と動詞(散歩させる)の2つの役割を動詞walkが担っています。
一方自動詞の場合は、動詞walkに助詞の働きは含まれません。そのため、自動詞に助詞が必要な場合は、前置詞とともに使う必要があります。
また受動態として使えるのは、他動詞だけです。これは、受け身になる場合、主格と目的格の2つが必要なためです。目的語を主語にするのが受動態であるため、目的語がない自動詞は受け身にできません。
多いのは自動詞?他動詞?
自動詞と他動詞、どっちが多いと思いますか?使われる頻度で比べると、他動詞の方が圧倒的に多いです。
そのため、英文を読むときは、まず他動詞として使われている可能性を考えましょう。自動詞と他動詞とでは意味が異なる場合もあるため、最初から意味を決めつけず、目的語に当たる部分はないか探してみてください。
前の章で紹介した例文でいえば、He walked.なら自動詞で、「彼は歩いた」という意味になります。一方、He walkedの後にthe dogがあれば他動詞で、「犬を散歩させた」という意味になりますよね。
いきなり意味から文意を理解しようとすると、
①walkだから歩くという意味だ!
②あれ?じゃあthe dogは?
という流れになってしまいます。
そのため、最初の段階では意味を決めつけないことが大切です。
流れとしては、
①動詞は他動詞として使われる機会が圧倒的に多い
②目的語に当たる部分はthe dogだ
③自動詞だと歩くだけど、他動詞だと~を散歩させるという意味だから、犬を散歩させるという意味だ!
となり、正解にたどり着きやすくなります。ぜひ、心がけてみてくださいね。
>>layとlieの意味と違い|活用(過去形/過去分詞/ing形)の発音・例文・覚え方
英語の自動詞と他動詞の見分け方|助詞や前置詞で区別するのがポイント

英文に登場する動詞が自動詞なのか他動詞なのかは、どう判断すればよいのでしょうか。He walked.やHe walked the dog.のように簡単な文章であれば、目的語の存在はすぐにわかります。しかし、副詞や形容詞など多くの単語が含まれると、難易度は上がっていきます。
ここでは、自動詞と他動詞の見分け方について見てみましょう。
英語の自動詞と他動詞の見分け方①動詞に「を」「に」が含まれているか
動詞が他動詞として使われる場合、をやになどの助詞が動詞の意味に含まれると説明しました。これが、英文中で自動詞か他動詞かを見分けるポイントのひとつになります。
助詞を含む動詞は必ず目的語を必要とするため、動詞の後に目的語があるかをチェックすればOKです。目的語があり、動詞が助詞の意味も含んでいれば他動詞です。
英語の自動詞と他動詞の見分け方②動詞の後に前置詞があるか
2つめのポイントは、動詞の後に前置詞があるかどうかです。以下の例文を見てみましょう。
彼は公園へ歩いていった。
He walked to the park.
walkの後にtoという前置詞があります。ここでは、「公園へ」という助詞の働きを前置詞toが務めているため、動詞walkに助詞は含まれていません。したがって、動詞walkは自動詞だと判断できます。
英語の自動詞と他動詞の見分け方③他動詞の後に副詞を挟むパターン
中には、他動詞の後に副詞を挟むパターンもあります。
副詞は自由な場所に置けるため、動詞+副詞+目的語といった語順になることもあります。そのため、「動詞の後ろに目的語がないから自動詞だ」と考えてしまうと、意味を正しく理解できません。
副詞が目的語の前に来ることも考えながら、目的語探しをしてくださいね。
英語の自動詞と他動詞の見分け方④自動詞にも他動詞にもなる動詞
すでに説明した通り、動詞ごとに自動詞か他動詞かが決まっているわけではありません。自動詞でも他動詞でも使える動詞は多い上に意味が変わることもあるため、自動詞か他動詞かを見分けて、文脈に合った正しい意味を見つけることが大切です。
英語の自動詞と他動詞の見分け方⑤TOEICにもよく出る!discussはどっち?
中には、判断に迷う動詞もあります。勘違いしやすい単語としてよく取り上げられるのがdiscussです。あなたは自動詞と他動詞、どっちだと思いますか?
discussは~について議論するという意味の動詞。~についてと訳されることが多いため、discuss aboutで自動詞と考える人が多いのです。しかし実は他動詞で、aboutは必要ないのです。
似た意味を持つdebateやargueは、aboutを伴った自動詞として使われることもあります。とても混同しやすいですが、間違わないように注意しましょう。
英語の自動詞と他動詞の見分け方⑥連結動詞のパターン
動詞の後に名詞が来たら他動詞、と思いたいところですが、実は連結動詞というパターンもあります。
連結動詞としてよく知られているのがbecomeです。~になるという意味で覚えている方も多いのではないでしょうか。becomeの後には必ず名詞などの単語が来るため他動詞、と言いたいところですが、実は違います。
becomeの後に来る名詞は目的語ではなく、補語なのです。
つまり連結動詞は、主語+動詞+補語の第2文型で用いられる動詞のこと。主語と補語をイコールで繋ぐ、つまり連結する動詞ということですね。連結動詞は自動詞に分類されますが、他の自動詞とは異なり補語が必要なため、不完全自動詞と呼ばれることもあります。
becomeは他動詞としても使えますが、その場合、~は…に似合うという意味になるため注意してくださいね。
連結動詞はbecomeの他にもいろいろありますが、もっともよく使われるのはbe動詞でしょう。be動詞も連結動詞なので自動詞ですが、現在進行形や受動態などの場合は助動詞として働きます。
連結動詞の見分け方に迷ったら、動詞をイコールの記号に変えてみてください。両者の関係がイコールで結べるなら連結動詞です。
He is my friend.を例に取れば、He=my friendで結べますよね。He became a teacher.はHe=a teacherで結べます。
ではHe walked the dog.は?He=the dogではないですよね。なので連結動詞ではないとわかります。連結動詞として使える動詞には他にもseem、sound、look、feel、keep、get、fall、turnなどがあります。
英語の自動詞と他動詞の見分け方⑦オススメの覚え方はセットで暗記すること
自動詞と他動詞の区別がつきにくい場合は、簡単な例文をまとめてセット暗記してしまうのがオススメ。目的語が必要なら目的語セットにし、前置詞が必要なら前置詞セットとして一緒に暗記してしまうわけですね。
例えばmarry(結婚する)はmarry me!(結婚して)で覚えてしまうと、marryの他動詞としての用法を覚えられます。しかしmarryには自動詞としての用法もあり、She married very young.(彼女はかなり若いうちに結婚した)といった使い方もできるのです。このように、どちらもセットでまとめて覚えてしまいましょう。
英作文の際にmarryはどっちだっけ?と思ったら、marry me!とShe married very young.の2文を思い出し、応用すればOKです。
恋人へ愛を伝える英語フレーズの記事はこちらです。
英語の自動詞と他動詞の一覧表|まとめて覚えるのがオススメ
| 自動詞 | 意味 | 他動詞 |
| listen to |
~を聞く | hear |
| speak to |
~に話しかける | address |
| argue about |
~を議論する | discuss |
| arrive at |
~に到着する | reach |
| refer to |
~に言及する | mention |
| appear on appear in |
~に出席する | attend |
| be similar to |
~に似ている | resemble |
| come into |
~に入る | enter |
類語を、自動詞と他動詞とでまとめて覚えておくのも便利です。自動詞は前置詞などとセットで、他動詞の単語と関連付けて覚えてしまうわけですね。
よく出る表現をいくつかピックアップして表にまとめてみました。是非参考にしてくださいね。
that節で他動詞になる動詞一覧
| 自動詞 | 意味 | 他動詞 |
| agree with |
~に賛成する | agree that |
| boast of boast about |
~を自慢する | boast that |
| complain of complain about |
~について不平を言う | complain that |
| hope for |
~を望む | hope that |
| think of think about |
~について考える | think that |
動詞の中には、本来ならば自動詞として前置詞と共に使われるところを、目的語にthat節を置くことで他動詞として扱うものがあります。一覧表で整理していきましょう。
>>discuss aboutは間違い?他動詞discuss withの正しい使い方
英語の自動詞と他動詞の見分け方をわかりやすく例文で紹介

最後に、自動詞と他動詞の見分け方を例文でご紹介します。まずは例文だけを見て、自動詞か他動詞か当ててみてくださいね。
英語の自動詞か他動詞かを見分ける例文①change
①シェリーは高飛車な妻に変わった。
Shelley changed to a high-handed wife.
②シェリーは勤務先を変えた。
Shelley changed her workplace.
まずはchangeから見ていきましょう。どちらか見分けることができたでしょうか?これは基本通りの構文なので、比較的簡単かもしれません。
①はchanged+前置詞toです。前置詞を伴うのは?そう、自動詞ですね。
②はchanged+名詞で、動詞の後に名詞が来ています。Shelley=her workplaceにはなりませんから、連結動詞ではありません。つまり、名詞は目的語です。動詞+目的語で、目的語が必要なのは?そう、他動詞ですね。high-handedは「高飛車な」という意味を持ちます。
英語の自動詞か他動詞かを見分ける例文②hit
①トムが対戦相手に殴りかかった。
Tom hit at his opponent.
②トムが対戦相手を殴った。
Tom hit his opponent.
続いて、hitです。構文自体はシンプルですが、日本語の意味に引っ張られると迷いやすいのではないでしょうか。
hitは殴るという意味を持ちます。殴る対象を必要とする動作ですから、他動詞として使われます。動作の対象はhis opponent、つまり彼の対戦相手ですね。
①ではhit+前置詞atとなっています。前置詞を伴う動詞は?…そう、自動詞ですね。
②の方はhit+名詞です。Tom=his opponentではありませんから、連結動詞ではありません。ということは目的語です。目的語を伴う動詞は?…そう、他動詞ですね。
自動詞や他動詞で意味が変わる単語もありますが、hitはどちらも「殴る」です。
①と②の違いは、hitが自動詞となり、前置詞atが追加されている点。ただしこの言い回しは、atを用いることで異なるニュアンスが表現されているのです。
この場合の前置詞atは、動作の方向を表しています。hitという動作がhis opponentの方へと向かったという動作に焦点が当てられているのです。殴りかかったと和訳されているように、相手に向かう動作を表現するためにatが足され、hitが自動詞となっているわけです。
英語の自動詞か他動詞かを見分ける例文③stop
①私の父は飲むために足を止めた。
My father stopped to drink.
②私の父はお酒を飲むのを止めた。
My father stopped drinking.
こちらは、色々と迷うポイントがありますね。しかし、意味で決めつけようとせず、自動詞か他動詞かの判断は文の構成で見極めましょう。
①はto不定詞が、②は動名詞がそれぞれ使われています。さて、わかったでしょうか?
それでは答え合わせしましょう。①は前置詞toがあるため、自動詞。②は動詞の後に名詞としての役割を持つ動名詞があるため、他動詞です。
動詞の後に来るto不定詞と動名詞は混同しやすいですね。正しく使い分けるために、ここでそれぞれが持つニュアンスをしっかり把握しておきましょう。
一般的にto不定詞は非現実を表し、動名詞は現実を表します。①のto drinkの場合、これから飲むためにstopしたわけですから、drinkという動作はまだ行われていません。そのため、非現実のニュアンスを持つto不定詞が使われているのです。
一方②のdrinkingは、お酒を飲むのを止めたという意味です。つまりdrinkという動作は既に行われていますよね。そのため、現実を表す動名詞が使われています。
ちなみに、不定詞におけるtoの後の原形動詞は名詞的性質を持っているので、前置詞to+原形動詞が成り立っているのです。
動名詞と不定詞についての記事はこちらで詳しく解説しています。
>>動詞の前にtoをつける時と、動詞の後にingをつける時。動名詞と不定詞について
自動詞と他動詞の違いと見分け方|覚え方もわかりやすく例文と一覧で解説まとめ

ここまで、自動詞と他動詞の違いや見分け方を、例文や一覧表を使って紹介してきました。
とても良く目にするものだけに、「覚えるしかない」と諦めている方も多いはず。簡単な文章であれば、日本語訳を元に見分けることができるかもしれません。でも、きちんと意味を理解してしまえば、日本語訳に頼らずとも見分けることができます。
今回ご紹介した内容は、どれも実用的で使えるものばかりです。ぜひ日常の中でたくさん活用していただき、自動詞と他動詞の違いを体で覚えていってくださいね!